飯豊町/Iide
【雪国の暮らし息づく山麓の村】
山形県の西南部の厳しい冬と向き合いながら生活を営んできたこの村は、
広大な平野に広がる水田地帯と、
里山文化息づく山麓集落という2つの顔を持っている。
英国の紀行作家イザベラ・バードの著書「日本奥地紀行」の中で、
この置賜地方の風景を「東洋のアルカディア(桃源郷)」と称したように、
冬が終わりを告げると魔法をかけたかのように村全体が色づき始める。
田園に日が差し込みだす朝に田んぼのあぜ道を歩けば、
眩いほどに輝くこの村の美しさに出会うだろう。

山形県の西南部の厳しい冬と向き合いながら生活を営んできたこの村は、
広大な平野に広がる水田地帯と、
里山文化息づく山麓集落という2つの顔を持っている。
英国の紀行作家イザベラ・バードの著書「日本奥地紀行」の中で、
この置賜地方の風景を「東洋のアルカディア(桃源郷)」と称したように、
冬が終わりを告げると魔法をかけたかのように村全体が色づき始める。
田園に日が差し込みだす朝に田んぼのあぜ道を歩けば、
眩いほどに輝くこの村の美しさに出会うだろう。
目次【本ページの内容】

山形県の西南部の厳しい冬と向き合いながら生活を営んできたこの村は、広大な平野に広がる水田地帯と、里山文化息づく山麓集落という2つの顔を持っている。
英国の紀行作家イザベラ・バードの著書「日本奥地紀行」の中で、この置賜地方の風景を「東洋のアルカディア(桃源郷)」と称したように、冬が終わりを告げると魔法をかけたかのように村全体が色づき始める。
田園に日が差し込みだす朝に田んぼのあぜ道を歩けば、眩いほどに輝くこの村の美しさに出会うだろう。
目次【本ページの内容】

飯豊連峰を源流とする清らかな水が肥沃な扇状地を形成することから、飯豊町では稲作栽培が盛んに行われてきた。水田に養分を運ぶ水の流れが得られる場所に、それぞれの農家が屋敷を構えたことにより散居集落という独特の景観が形成された。
50万本以上のユリの花が咲き誇るどんでん平ゆり園に設けられた展望台は、そんな田園散居集落を一望できるパノラマスポットとなっている。また冬になると北西からの冷たい季節風が流れ込むため、防風や防雪のために家の西側に屋敷林を配しているのもこの村の特徴である。

飯豊連峰を源流とする清らかな水が肥沃な扇状地を形成することから、飯豊町では稲作栽培が盛んに行われてきた。
水田に養分を運ぶ水の流れが得られる場所に、それぞれの農家が屋敷を構えたことにより散居集落という独特の景観が形成された。
50万本以上のユリの花が咲き誇るどんでん平ゆり園に設けられた展望台は、そんな田園散居集落を一望できるパノラマスポットとなっている。
また冬になると北西からの冷たい季節風が流れ込むため、防風や防雪のために家の西側に屋敷林を配しているのもこの村の特徴である。
広大な水田地帯を超え、山道を上った先にたどり着くのが中津川集落である。県下でも有数の豪雪地帯として知られ、冬には道の両脇が人の背丈に2倍ほどの高さに積み上がる。中津川地区に残る中門造りと言われる民家は、馬と人間が共存できる造りとなっている。
樹齢400年を超える杉林に囲まれた厳かな空間に佇むのは、木造の岩倉神社。飯豊山信仰の入口として多くの人々が参拝し、室町時代初期(14世紀)に作られた不動明王像が祀られている。また植物に宿る神を崇めるために建てられた石碑、草木塔も土着の文化として集落に点在している。


広大な水田地帯を超え、山道を上った先にたどり着くのが中津川集落である。
県下でも有数の豪雪地帯として知られ、冬には道の両脇が人の背丈に2倍ほどの高さに積み上がる。
中津川地区に残る中門造りと言われる民家は、馬と人間が共存できる造りとなっている。
樹齢400年を超える杉林に囲まれた厳かな空間に佇むのは、木造の岩倉神社。
飯豊山信仰の入口として多くの人々が参拝し、室町時代初期(14世紀)に作られた不動明王像が祀られている。
また植物に宿る神を崇めるために建てられた石碑、草木塔も土着の文化として集落に点在している。

厳しい冬を乗り越えるために、豊かな生活の知恵も受け継がれてきた。特に菅笠やござ織りといった伝統工芸品は、江戸時代より長い冬の生活を支える生業として受け継がれてきた。今日でも山形市で開催される「花笠まつり」に用いられる多くの花笠が、この中津川集落で作られている。
また山菜などをつかった保存食を使った料理は、この村の郷土食として今日でも親しまれている。丁寧に調理された品々を味わえば素朴で自然な旨味が口いっぱいに広がり、現代の時の流れの速さの中で忘れかけていた優しい温もりを感じることが出来る。

厳しい冬を乗り越えるために、豊かな生活の知恵も受け継がれてきた。
特に菅笠やござ織りといった伝統工芸品は、江戸時代より長い冬の生活を支える生業として受け継がれてきた。
今日でも山形市で開催される「花笠まつり」に用いられる多くの花笠が、この中津川集落で作られている。
また山菜などをつかった保存食を使った料理は、この村の郷土食として今日でも親しまれている。
丁寧に調理された品々を味わえば素朴で自然な旨味が口いっぱいに広がり、現代の時の流れの速さの中で忘れかけていた優しい温もりを感じることが出来る。
毎年3m近く積る雪を有効活用するために作られたのが、雪を貯蔵することで夏季にも0~4度の温度と適度な湿度を保つ雪室施設。じゃがいもなどは低温で貯蔵されることで、でんぷんが糖分へと変化し甘みが増すことから、「雪室じゃがいも」としてブランド化されてこの街の特産品となっている。
また毎年7月末に開催される「SNOWえっぐフェスティバル」は、全国的にも珍しい真夏の雪まつりとして知られる。1991年に地元の有志が協力して雪山を作り、夏まで保存する実験を行ったことをきっかけとしており、今日では中津川集落屈指の人気のイベントとなっている。


毎年3m近く積る雪を有効活用するために作られたのが、雪を貯蔵することで夏季にも0~4度の温度と適度な湿度を保つ雪室施設。
じゃがいもなどは低温で貯蔵されることで、でんぷんが糖分へと変化し甘みが増すことから、「雪室じゃがいも」としてブランド化されてこの街の特産品となっている。
また毎年7月末に開催される「SNOWえっぐフェスティバル」は、全国的にも珍しい真夏の雪まつりとして知られる。
1991年に地元の有志が協力して雪山を作り、夏まで保存する実験を行ったことをきっかけとしており、今日では中津川集落屈指の人気のイベントとなっている。
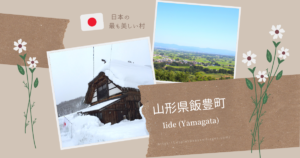
山形県飯豊町
面積:329.41km2
人口:6,965人(2018年4月1日現在)
2018年5月14日:ページ更新
2021年8月29日:ページ更新

村内がオレンジに輝く夕暮れ時や、夜のライトアップ、朝霧に包まれた街並みなど、時間によって様々な表情を見せるのが美しい村の魅力。
飯豊町の中津川集落には、農家民宿が点在し家庭的で温かい雰囲気が特に人気となっています。その中でも特にお勧めの宿を紹介させて頂きますので、参考にして頂ければ幸いです。
その名の通り、囲炉裏を囲んで食べる料理が人気の宿。ヤマメなどの川魚を使った料理や、伝統の山菜料理などは絶品です。日本の田舎らしい懐かしさを感じる建物で、ゆっくりとした里山の時間を体験したいという方にはお勧めです。料金は1名2食付きで6,800円からです。
【一緒に訪れたい美しい村】
飯豊町から車で1時間20分(70km)
飯豊町から車で2時間20分(110km)